3月に入り、季節は春に移っている。気温も暖かくなり、町中には梅が咲く季節となった。キャンパスの中も活気づいているようにも見える。今月のレポートのテーマは、「中国語の勉強方法」である。浅学非才の身ではあるが、筆者の勉強法についていくらか述べてみたいと思う。
筆者が中国語に初めて触れたのは大学一年生の時である。それ以降中国語についての勉強を断続的にではあるが継続してきた。大学生の時は基本的な文法や単語などを授業で学んでいたように思う。大学院に進学した後は外国語のスクールでオンライン授業を受けたり、インターネットで先生をお願いして勉強をしたりしていた。また、研究室の中国人留学生にお願いをして教えて貰ってもいた。現在は中国語の授業も開講している語学スクールもあるし、日本の大学の中にもいわゆる孔子学院が設置されている学校もある。其の他、上述の通りインターネットを利用して学ぶことも可能である。勉強法も多様化していると言える。
留学開始以降の勉強についての話もしていこう。とはいえ以前のレポートでも述べた内容が含まれるので、簡単に述べる。まずは、留学先での授業について言及する。浙江大学では外国人向けの中国語の授業を開講しているので、筆者はそちらに出席をしている。レベル別に複数の授業が開講されており、些か選択には難儀した。とてもわかりやすい授業に感じている。また、現地の中国人と知り合いになって教えてもらっている。このように個人的に教えて貰うのは効果的であると思われる。また、動画サイトで中国語を聞くといった試みも行なっている。
最後に、これまで勉強してきた中で気づいたことを述べたい。中国語学習も英語学習同様、単語の暗記というのは大切であると言える。とはいえ、日本で出版されている中国語の単語帳は多くない。教科書に載っている単語を押さえておくことや、生活の中で単語を知っていく努力は必要であると思う。筆者にとっても課題であると思われるので、今後も努力していきたい。また、「内容を理解」することと「使う」ことはやはり異なる。試験で回答する時には問題ないことであっても、実際に使う時には中々言葉が出てこないものである。やはり実際に「使う」練習が大切なのだと感じる。中国語を勉強する時にはよく「多听,多说,多练习」といったような言葉を耳にすることがあるが、なるほどと得心する毎日である。

町中に花が多くみられるようになった
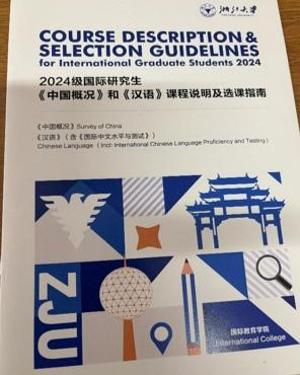
レベルや目的に応じたいくつかの授業が開講されている
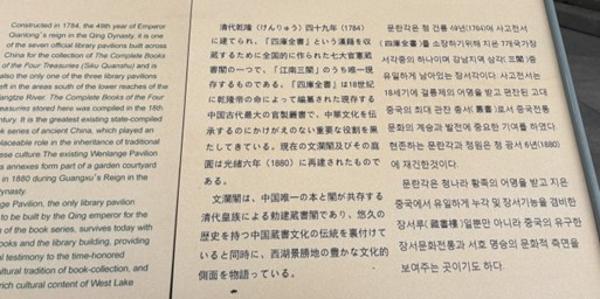
この写真の日本語は分かりやすい




