猛烈な勢いでデジタル化が進み、市民生活の末端にまで浸透している中国。キャッシュレス、チケットレスなどは当たり前で、多くの人はその便利さを享受しているのだろうが、アプリを自在に使いこなせない筆者のようなアナログ人間にとっては、昔と比べて〝ストレス〟とも向き合わざるを得ない社会になってしまった。
そこで今回は、筆者のコレクションの中から、懐かしい紙幣を紹介したいと思う。レトロなデザインにノスタルジーを感じるだけではなく、券面から当時の時代背景もみえてくる。
消えた「角」と「分」
最後に中国を訪問したのは、コロナ禍に見舞われた直前だが、すでに当時からあらゆる場面でキャッシュレスは一般的になっていた。ストリートミュージシャンへの「投げ銭」ですらQRコードにスマホをかざす人が多く、「日本は遅れているな」と感心したのを思い出す。
その後、中国社会はさらにデジタル化が進み、広州在住の知人いわく「最後に現金を使ったのがいつか、思い出せないくらい」とのこと。筆者は近く久しぶりに訪中する予定だが、そんな超ハイテク社会に順応できるのか不安で仕方がない。
写真①から③は、かつて流通していた小額紙幣である。中国の通貨は、ご存知の通り「元」であるが、その下に「角」「分」という単位があり、1元=10角、1角=10分。元、角は書き言葉で、話し言葉では、塊の簡体字である「块」「毛」(分はそのまま)を用いる。



余談だが、野球の世界では打率を2割8分5厘などというが、同率の場合、厘のあとに毛が続く。このふだんの生活ではほとんど目にしない分、厘、毛という単位は、中国にルーツがあるそうだ。
もはや角や分が日常で使われる機会はないが、筆者が湖南省に留学していた1990年代後半には、まだバスの運賃や饅頭など、いろいろな場面で角が存在感を示していた。それぞれ硬貨も併用されていたが、地方では断然紙幣(ほとんどがボロボロだったが)のほうが多かった記憶がある。
分の紙幣は1953年発行と印刷されているが、トラック、飛行機、船舶の図柄が近代化をめざす国や人民の気概を象徴しているようで興味深い。明るい色使いもよく、Z世代がみたら「エモい」との感想を口にするのではなかろうか。
1角紙幣(写真④)の発行年は不明だが、描かれているのは溌溂とした農民の姿。これも農村から国を元気にしていこうという時代の空気を感じさせる。写真⑤の10元札をみて、不自然な点に気付いた人は相当な中国通といえるだろう。実はニセ札なのである。


あまり使われなくなったとはいえ、2015年に発行された現在の紙幣には高度な偽造防止技術が施されているが、ひと昔前は、ニセ札対策が大きな課題となっていた。
高額紙幣で支払うと、鑑別の精度は分からないが、必ず「点鈔機」と呼ばれる紙幣チェッカーに通された。この機械を持っていない個人商店や露店などでは、紙幣を高くかざし、光を当て、しつこいくらいに確認するのが慣習だった。
運悪くつかまされた者は泣き寝入りするしかない。そのため、ババ抜きのように相手に渡してしまおうと必死になるのだが、本物との違いに疎い外国人は格好のカモだったはずだ。
この紙幣も、よくみると色が若干薄く、印刷もやや粗い気がする。100元や50元ならまだしも、犯罪グループがコスパの悪い10元札を偽造したのは、「10元なら警戒が甘くなる」と考えたためだろうか。
急速にキャッシュレスが普及した背景には、技術の進歩に加え、大量のニセ札を無効化する目的もあったとされる。また、経済大国となった中国においては、最高額が100元では枚数がかさみ不便なため、1000元以上の札が検討されたこともあったのだが、やはりニセ札のリスクが高いことを理由に導入は見送られた。こうした諸々の問題をキャッシュレスで一気に解決した中国は凄いと思う。
外国人が手にした兌換券
写真⑥は、一見、ふつうの1角札のようにみえるが、これは外国人専用の「兌換券」と呼ばれるものである。中国政府は外貨管理の一環として、1979年に制度を導入し、1995年まで続けられた。

廃止からまだ30年なので、「使ったことがある」と懐かしく感じる読者も少なくないのでは。別の見方をすれば、わずか30年の間に完全キャッシュレス社会を実現したのだから、いかに驚異的なスピードで発展してきたかが分かる。
外国人が両替した際、人民元ではなく、この兌換券を渡された。人民元と等価であったが、使用できる場所は限られており、外国人専用の百貨店や高級店が中心だった。
年輩の知人が兌換券にまつわるこんなエピソードを聞かせてくれた。
その後の中国のめざましい経済成長は周知のとおり。兌換券の時代は改革開放政策が走り出した時期と合致しており、政策の成功が兌換券を不要にしたといえるかもしれない。
写真⑦から⑩は、兌換券が登場する以前の「糧票」である。「市斤」は 500g のこと。1965年の数字がみえるのは、全国共通で使用できるもので、橋がデザインされているのは、湖南省限定のものだ。


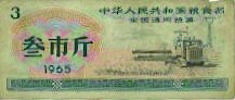
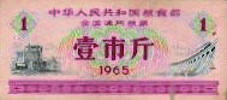
橋が架かっている大きな川は、長沙市を流れる湘江だろう。湘江の中洲にある橘子洲は、現在すべての紙幣で肖像に描かれている同省出身の毛沢東が、よく泳いでいた「聖地」のひとつとして知られ、巨大な胸像が設けられている。
筆者は湘江大橋を渡った先にある湖南師範大学に留学していたので、ひときわ親近感を覚える。これらの貴重なコレクションは、現地でお世話になった方が譲ってくださったものだが、「捨てるほどあるから」と笑っていた。
裏面には発行元である「湖南省革命委員会糧食局」の文字も。当時、毛を輩出した湖南省は「革命」という言葉が最も似合う場所であった。
糧票の歴史は古く、1949年の建国時から、さまざまなタイプが使われていた。ある意味、現金以上の価値があり、これがなければ、米や小麦、食用油など、生きるために必要な物資は入手できなかったのである。農村から食糧を提供されていた都市部での需要が高く、北京市では1993年まで残っていたという。
糧票が消え、兌換券が消え、中国は豊かになっていった。そして、紙幣までもが表舞台から消えたいま、新たな時代へ向かって社会は変化を遂げている。
(内海達志)





